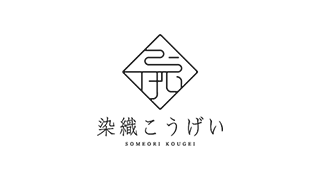今月は「松原染織工房 日本の藍 不易流行」を浜松店・神戸店にて開催いたします。
神戸展 6月11日(木)~15日(月) 松原孝司氏 来場日 12日(金)~14日(日)
浜松展 6月25日(木)~29日(月) 松原孝司氏 来場日 26日(金)~28日(日)
昭和30年に重要無形文化財(人間国宝)に認定された故 松原定吉氏の
10男 興七氏 、5男 故 福与氏の2男 孝司氏 、9男 故 八光氏の長男 忠氏の三人により「長板中形」の技術は守られ継承されています。
「他の文化の産物を利用して造り出したものは、
伝統工芸というよりも、現代工芸であるといえましょう」
工房、道具、材料、全てを伝承して、今日まで技術を守り続けます。

長板は約6m50cm 重さは約60kgあり、下の馬と呼ばれる上に置き染付作業をします。
地面から長板までの距離は160cmで身をかがめなければ入れませんが、これは60kgの長板を一人で上げ下ろしするには良い高さなのです。
馬も低いのですが低いほど片付するときに真上の視線位置を確保出来ます。
いずれにしろどちらも腰への負担は大変です。

型紙に糊付けする木ベラも全て手作りで型紙により使い分けます。

型付用の糊は米糠で毎日造り変えます。(雨の日は干せないので作りません)
藍甕を冬の時期温めるのもガス、電気に頼らず木グズを甕の間に敷き詰めて蚊取り線香のように燃やします。
本物の藍の話、作品を是非この機会にお楽しみください。